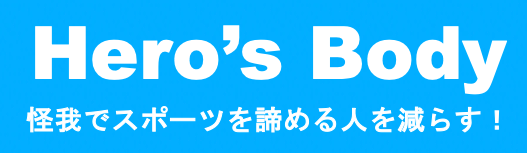練習を増やせば増やすほど速くなれると信じているランナーは多いことかと思います。
実はその頑張りが自己ベスト更新を遠ざけ、パフォーマンス低下を引き起こしている原因になっているかもしれません。
オーバーリーチングとは?
機能的・非機能的オーバーリーチング
オーバーリーチングとは十分な休養がない状態での個人の能力を超えるトレーニングを指します。
機能的オーバーリーチングはパフォーマンスアップを伴う疲労であり、非機能的オーバーリーチングはパフォーマンスアップを伴わない過度な疲労となります。
基本的にランニングなどの持久系競技は運動量の総量が増えた方がパフォーマンスが高まりやすい傾向にあります。
しかし、練習量を増やせば増やすほどパフォーマンスが上がり続けるわけではなく、どこかでパフォーマンスアップにつながらなくなります。
過度な練習を避けて、健全な範囲内での練習に留めることがパフォーマンスアップのポイントであり、
この機能的・非機能的な疲労の境目を見極めることが持久系競技では重要になってきます。
オーバートレーニングとの違い
非機能的オーバーリーチングは数日から数週間で回復し、パフォーマンスの低下はみられるものの練習自体を続けることができます。
しかし、オーバートレーニング症候群は練習を続けることすら困難な状態であることが多く、軽い練習にすら拒絶反応を示し、回復にも数か月から年単位を要することも珍しくありません。
パフォーマンスが低下し始める非機能的オーバーリーチングの段階で休養を増やさないと、いずれオーバートレーニングによる長期離脱を引き起こしてしまうリスクがあります。

オーバーリーチングのサイン
主観的な疲労度
過度な疲労がかかっていないか判断するのに極めて重要なのが主観的な疲労度です。
主観的だから当てにならないと思うかもしれませんが、実際にオーバートレーニングの兆候として主観的な疲労感のほうが客観的な医学データよりも有用であることが多いという研究結果が報告されています1。
ストレスホルモンやヘモグロビンなどといった医学データは早い段階での疲労度を掴むのには適しておらず、慢性的に疲労が蓄積していかないと数値に表れにくいという欠点があります。
そして、ランニングの疲労は練習の組み立て方だけに限ったものだけではなく、私生活のストレスも練習の疲労度に影響してきます。
仕事での精神的ストレスや人間関係のトラブルといったトレーニング以外のストレスによってリカバリー能力が低下することがあります2。
このように私生活でのストレスも影響するため主観的な疲労度が役立つわけです。
体重の減少
体重が減少していくと疲れが溜まりやすくなり、トレーニング効果が低下してしまう可能性があります。
食事量が足りていないとオーバートレーニングに似たような症状が出ることが報告されています3。
パフォーマンスが維持できているような健全な減量であるならば問題はありませんが、たくさん走っているランナーにとって健全な減量は思っている以上に難しいものです。
実際に食事が足りていないランナーはパフォーマンスが低下しやすいことが報告されており4、減量がパフォーマンスアップに結び付かない事例も多くあります。
特に体重の低下とパフォーマンスの低下の両方がみられる場合にはリカバリーが追いついていない可能性が高く、やり方を見直す必要があると思います。
私自身も減量を必死に頑張っていた時期があり、甘いものや油をできるだけとらない、という偏った食生活を1年ほど続けていました。パフォーマンスアップには大して役には立たず、むしろ疲れが溜まってパフォーマンス低下を引き起こしてしまうことが度々ありました。
そして、体重が減ってガリガリにやせ細っていくと疲れが溜まりやすくなるだけでなく、疲労骨折を引き起こして長期離脱してしまうリスクもあるので注意が必要です。
-

ランナーの疲労骨折の原因と対策について
続きを見る
運動量
一般的に走行距離が多いランナーのほうが競技成績が良い傾向にあり、運動量を増やすことは大切なことです。
しかし、走行距離を増やしているのにパフォーマンスアップにつながらないのは適切な運動量を超えてしまっていて、過剰な負荷がかかってリカバリーが追いついていない可能性があります。
特に運動量が増えているのにパフォーマンスが低下している状況では、運動量を減らして休みを増やす必要があると思います。
ここで練習の負荷が足りないからかもしれないと考え、さらに激しいトレーニングで追い込んでも状況が改善するとは限らず、むしろ疲労の蓄積によってさらなるパフォーマンス低下を招いてしまうことがあります。
最悪のケースではオーバートレーニングによって数か月から1年といった長期離脱を余儀なくされてしまう可能性もあります。
心拍数
心拍数の変化は疲労を把握するのに役立つと言われています。
起床時の心拍数の上昇が続いていると疲労が蓄積している可能性がありますし、練習量が増えているのに運動時の心拍数上昇が何日も続くようであればパフォーマンス低下の疑いがあります。

近年ではスマートウォッチが疲労の蓄積を通知してくれるようになりました。
スマートウォッチの精度は限られているからと、通知を完全に無視するというのは得策ではありません。
スマートウォッチからの通知があり、主観的にも疲労を感じている場合には潔く休みをとったほうが賢明です。
主観的な感覚と心拍数データなど、複数のフラグが立っている場合には疲労が溜まっている可能性が高いと言えます。
、
血液検査
血液検査をすることで貧血などの栄養不足を発見することができ、オーバートレーニングの予防に役立ちます。
血液データは客観的な身体のコンディションを示すことができ、主観的な感覚ではわからない身体の異常を見つけることができます。

とはいえ早い段階での疲労を血液検査で検出できるかというと微妙なところですし、オーバートレーニング症候群であっても血液検査に異常が出ないのは珍しいことではありません。
このため血液検査に異常がないからといって健康状態や練習量に問題がないというお墨付きが得られるわけではありません。
オーバーリーチングを防ぐための判断
健全な疲労なのか、これ以上追い込んでしまうとパフォーマンス低下を引き起こすか、その境目を判断することは難しいものがあります。
リカバリー能力は個人差が大きく、練習内容の好みによっても疲労の溜まり方が違い、客観的で明確な基準があるわけではありません。
特に心拍数や医学データなどだけでは、もっと追い込んでいい疲れなのかどうかが判断しにくく、主観的な疲労度のほうが有用であることが多い傾向にあります5。
主観的な疲労感が大事と言われても、かなり曖昧でわかりにくいものがあると思います。
練習をしたくないという日だってあるだろうし、そういったときに頑張ったらパフォーマンスが良かったなんてこともあります。
それでも自分の身体の状態をうまく感じ取れること、身体の声に耳を傾けることができる人が記録を伸ばしやすいのかもしれません。
自分の感覚が頼りないのであれば、主観的な感覚と複数の客観的指標を参考にすることが役立ちます。
疲れている気がする、けれど頑張れば何とかなるかもしれないという判断に迷う状況では、心拍数などの客観的指標に疲労のフラグも出たら休むといった判断が賢明です。
主観的情報と客観的情報をうまく組み合わせることで過度な疲労を防ぎやすくなります。
トレーニングの中毒性について
休んだほうがいいと頭でわかっていてもトレーニングがやめられないという人もいるかもしれません。
私自身もトレーニングが大好きで練習を休むことができない人間でした。
ここにはランニングに対する考え方やライフスタイルが関わっている場合があり、正常な判断を下せずにパフォーマンス低下をみずから招いてしまうケースもあります。
価値観
ランニングで勝つためにはランニング中心の生活が有利と思うかもしれませんが、ランニングが人生で一番大切なものという価値観にはリスクもあります。
プロ選手や実業団選手のように走ることで対価を得ているのならば、ランニングが最も重要であり全てをかけるのは当然のことだと思います。
しかし、ランニングでお金を稼いでいないアマチュア選手が他のすべてを犠牲にしてランニングに打ち込むのは中毒気味であり、冷静な判断ができなくなるような精神状態に追い込まれる可能性があります。
特にお金がないのに多額の出費を続けてしまったり、恋人や家族関係に悪影響を与えてまでランニングに打ち込むのは健全ではなく、中毒気味であると思います。
気分転換
適度なランニングは気分転換になり、気持ちをリフレッシュさせる効果があります。
しかし、ランニングでしか気分転換ができないのであれば、それはランニング依存症といっても過言ではないかもしれません。
特にキツいトレーニングで快感を得ているのは心身を破滅させてしまうリスクがあります。
中断症状
走れない日が続くのはもどかしさを感じるランナーは少なくないかと思います。たくさん走りたいという気持ちがあるのは健全なものだと思います。
しかし、走れない日々が続いてしまうと気分が大きく落ち込み、普段できていた仕事や勉強などにも影響が出てしまうのはランニング中毒にかかっている可能性があります。
同じパターンから抜け出せない
過剰なトレーニングは良くないとわかっているのにやめられない、何度も怪我を繰り返してしまう、頭でわかっているのに同じパターンから抜け出せないのはランニング依存症の可能性があります。
この場合にはトレーニングのやり方を変えることや休養を多く取ることだけでなく、ランニング中毒になってしまっている価値観、ランニングに依存してしまっている生活を変えて、健全で楽しいランニングライフへの軌道修正が役立つかもしれません。
何を隠そう私自身がランニング中毒だった経験があります。
勝ちたいという気持ちが強くなっていき、私生活を犠牲にしてランニングに全てを捧げられるような環境を整えていきました。
しかし、そういった過激な考え方が過剰な練習につながり、極度の疲労でパフォーマンス低下を引き起こして、結果的には記録が伸びないばかりか心身がボロボロになってしまいました。
勝ちたいという気持ちだけが先走ってしまうのは逆効果だったということに気が付き、勝つためには余裕を持たせる必要があるということを悟りました。
このままではダメだと心機一転引っ越しをして、ランニング中心のライフスタイルを変え、家族との時間を増やしてランニング以外の趣味も持つようにしました。
その結果、破滅的なトレーニング思考から抜け出すことができ、記録向上につながりました。
まとめ
十分な休養を取らずに過度な練習を続けてしまうとパフォーマンスの低下につながります。
過度な疲労の定義はあいまいなものではありますが、主観的な感覚を軽視せず、客観的な情報も織り交ぜながら冷静に判断することが大切になります。
破滅的な思考やトレーニング中毒が冷静な判断を狂わせてしまうケースもあり、ライフスタイルを見直すことが役立つこともあります。
<参考文献>
- Saw AE, Main LC, Gastin PB. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. Br J Sports Med. 2016 Mar;50(5):281-91. doi: 10.1136/bjsports-2015-094758. Epub 2015 Sep 9. PMID: 26423706; PMCID: PMC4789708.
- Haghighat, Nekisa & Stull, Todd. (2024). Up-to-date understanding of overtraining syndrome and overlap with related disorders. Sports Psychiatry: Journal of Sports and Exercise Psychiatry. 3. 31-38. 10.1024/2674-0052/a000072.
- Stellingwerff T, Heikura IA, Meeusen R, Bermon S, Seiler S, Mountjoy ML, Burke LM. Overtraining Syndrome (OTS) and Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S): Shared Pathways, Symptoms and Complexities. Sports Med. 2021 Nov;51(11):2251-2280. doi: 10.1007/s40279-021-01491-0. Epub 2021 Jun 28. PMID: 34181189.
- Cupka M, Sedliak M. Hungry runners - low energy availability in male endurance athletes and its impact on performance and testosterone: mini-review. Eur J Transl Myol. 2023 Apr 11;33(2):11104. doi: 10.4081/ejtm.2023.11104. Erratum in: Eur J Transl Myol. 2025 Jun 27;35(2). doi: 10.4081/ejtm.2025.13900. PMID: 37052052; PMCID: PMC10388605.
- ten Haaf, Twan & van Staveren, Selma & Oudenhoven, Erik & Piacentini, Maria Francesca & Meeusen, Romain & Roelands, Bart & Koenderman, Leo & Daanen, Hein & Foster, Carl & de Koning, Jos. (2016). Subjective Fatigue and Readiness to Train May Predict Functional Overreaching After Only 3 Days of Cycling. International Journal of Sports Physiology and Performance. 12. 1-28. 10.1123/ijspp.2016-0404.
関連記事
-

ランナーに最適な月間走行距離とは?
続きを見る
-

ランナーが安全に走行距離を伸ばすポイント
続きを見る
-

クールダウンに軽い運動を取り入れる効果について
続きを見る